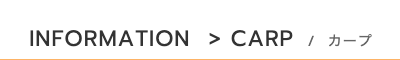江戸時代の代表的な読本のひとつに「雨月物語(うげつものがたり)」が挙げられます。上田秋成(うえだあきなり)が1776年に刊行した作品で、怪異小説9篇が記されています。その中に、「夢応の鯉魚(むおうのりぎょ)」という作品がありますので紹介します。
延長時代(923~931年)のお話です。大津の三井寺に興義(こうぎ)という僧侶がおりました。興義は絵の名手でしたが一般的な画題を選ばず、書く絵は魚ばかりでした。寝ても覚めても魚のことばかり考えて、時には夢で見た鯉を描いて壁に貼り、これを自ら「夢応の鯉魚」と呼びました。
ある年、興義は病気にかかり、七日間わずらった後に息が途絶えました。弟子たちが嘆き悲しんでいると、興義の心臓のあたりがかすかに暖かいことに気付きました。これはもしかしたらまだ生き返るかもしれないと思い、周りにすわって見守り続けたところ、3日過ぎたころ興義は夢から覚めたように起き上がりました。
生き返った興義は次のように語りました。この頃病気に苦しみ、辛さのあまりに自分が死んだのも知らないで、暑苦しい気分を冷ますために出かけました。やがて水辺に着いたところで深みに飛び込むと、冠と装束をつけた人が大魚にまたがって現れ、興義に金鯉の服を授けました。これを着てみると、なんと興義は一匹の鯉に変身したのです。
興義は琵琶湖を自由に泳ぎ回って遊んでいるうちに、とてもお腹がすいて食べ物が欲しくなりました。やがて漁師が釣り糸を垂れているのをみつけましたが、どうしようかと暫く考えました。しかし餌がとてもおいしそうだったのでついに我慢できなくなり、その餌を飲み込んでしまいました。とたんに興義は漁師に釣り上げられ、籠に入れられて自分の寺の檀家(だんか)である助の殿の館に連れて行かれました。
さっそく料理人が出てきて興義をまな板にのせ、左手で両目を押さえ、右手に研ぎすました包丁を持って今にも切りそうになりました。興義が苦しさのあまり大声を上げて泣き叫び、ついに切られると思った瞬間に目が覚めたのです。これは現代でいうところの臨死体験といえるでしょう。

出典)新潮日本古典集成「雨月物語 癇癖談」浅野三平:校注 新潮社 p64-65
あまりに不思議な話を目の当たりにしたので、助の殿の館では、残っていたその鯉の料理をすぐに湖に捨てました。
こうして興義は病気から回復し、後年まで天寿を全うしました。臨終の際、それまで描いた鯉魚の絵を数枚取り出して湖に散らしたところ、魚が抜け出して水中を泳いだと伝えられています。その後、弟子の成光(なりみつ)が興義の絵の技法を伝承し、みごとな鶏の絵を襖に描いたそうです(閑院の御殿の襖)。
参考文献
1)新潮日本古典集成 「雨月物語 癇癖談」 浅野三平:校注 新潮社
2)現代教養文庫 「雨月物語・春雨物語」 訳者:神保五彌、棚橋正博 社会思想社
3)「釣魚をめぐる博物誌」 長辻象平 角川書店